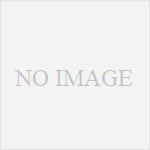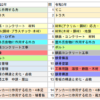今週は、上海で開催された中国最大級の屋外広告物展示会APPP EXPOに行ってきました。ちょうど10周年を迎えたアジア広告協会(Asian Advertisement Association)の式典や会議に参加するためです。それにしても、あまりの規模の大きさに本当に驚きました。東京のSDショウの10倍以上ありました。
さて、今回は屋外広告物の照明方法について解説します。この問題は、看板の内側に照明が入っているか(内照式・透過式)、外からスポットライト等で照らしているか(反射式)、光源がそのまま見えるか(自発光式)という照明方式の問題が最も多く出題されます。屋外広告の知識第四次改訂版のP76にあるので、参照ください。令和2年の問7が典型的な例です。
一方、看板内部の光の伝わり方についての問題も出題されます。こちらは、学識経験者ではなく、看板業の実務をしている人が問題を作成しているように見受けられ、実際に看板を製作していない方にはやや難しい内容です。屋外広告の知識ではp168に多少解説が出ていますが、幅広い知識が必要な問題です。
【問20】照明付きサインに関する記述として、適切なものはどれか。(令和3年度)
1.ネオン管は耐候性に優れ、瞬間的な変化が可能なことから、点滅式の広告物として一時代を築いた。
2.内照式照明製作では、一般的に蛍光灯(蛍光ランプ)を用いて、文字などの一部分を光るようにすることが多い。
3.蛍光灯(蛍光ランプ)を用いた薄型サインにエッジライトがある。これはアクリル板のエッジに光源を当て、光源と反対側のエッジを光らせる手法である。
4.照明を用いたサインでは点滅や調光によって表示を効果的に演出できるので、特に人が集中しやすい交差点等で自由な掲出が望ましい。
いかがでしょうか?正解は、1です。ネオン管を取り扱ったことのない方も多くなってきたと思いますが、ガラス管でできているので非常に耐候性が良いことと点滅を瞬間的に行えること、高電圧ですが消費電力が少ないことを覚えてしまいましょう。2の内照式照明は、箱型の看板の中に蛍光灯やLEDが入っていて、内側からアクリル板を均一に照らすことが最大の特徴です。ですから、一部分というのが誤りです。3は、アクリル板のエッジから光を入れると、反対側のエッジも確かに光りますが、面全体に光を拡散させるフィルムを貼ったり、アクリル板表面に細かい凹凸(キズ)を付けることで表示面全体を光らせる技法です。最近は、直下型LEDディスプレイという手法もあり、混同しないように気を付けましょう。4は、点滅や動きのあるサインが近くにあると信号が見にくくなるので逆に掲出は危険です。ちなみに名古屋市などでは、デジタルサイネージは交差点の信号機から5m以上離さなければならないという規則改正が令和6年より施行されています。